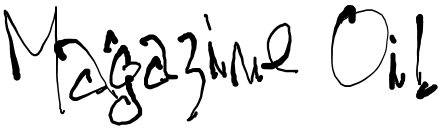やれ撃つな(小林一茶 ver.3)
信州でパルチザン発生の報。
「すみやかに鎮圧せよ」
県警からの電話でどやしつけられ、自転車で現場にむかう村の駐在。
鎮圧だって? パルチザンの鎮圧なんて、県警での訓練でもやったことがない。手順書などで見たおぼえもない。どうしたらいいんだろう。
考えがまとまらないまま、巡査は自転車を農家の庭に走り入れる。
縁側に腰かけて、小林一茶がこちらを見ている。
「一度目は悲劇として、二度目は喜劇としてだったかな」
ニヤリと笑う一茶。
「短絡だよ、俺が茶なんか立てると思うか?」
はぐらかされて対応に迷う駐在。
とても自分の手に負える人物ではない。一茶の笑いに射すくめられて駐在員はそう思う。インテリは苦手だ。しかもパルチザンの組織者だという。駐在所でふだん付き合ってきた村人とちがい、考えてることが見えない。けれども、ずる賢くて凶悪、そんな感じはする。どうしたらいいのか。それにパルチザンの蜂起が事実なら──どうも事実らしい──村の駐在ごときが扱える事件ではない。機動隊か自衛隊の出番ではないか。
駐在所に残してきた家族のことが脳裏をよぎる。
妻と二人の娘、それに駐在の四人で朝の食卓を囲んでいたところだった。
おかずは納豆、ノビルの味噌和え、タクワン漬け、フキノトウの吸い物、それに今朝は下の娘の誕生日ということで、山間の駐在宅としては多少おごった上等なアジの干物。
「おいしいね」と娘はよろこんでくれた。
下の娘は中一、上の娘は中三。
親の欲目で見てもせいぜい十人並の器量の娘たちだが、性格は悪くない。いや、特別な良い子たちだ。警察官の娘として恥ずかしくないしつけもしてある。勉強だって、そこそこの成績はもらってる。年ごろだから、クラスメートや先輩の男の子たちのことで彼女らが気もそぞろなのはわかっている。でも、それはそれ。けして軽はずみな行動に走るような子らではない。
県警から電話が入ったのは、駐在が「では、父さんも」と尾頭付きのつもりのアジに箸を伸ばしたところだった。
電話をかけてきたのは県警の幹部だった。それを知ったとたん、相手の名前は吹き飛んでしまった。幹部と直接話すなど、そんなことは一生ありえない──はずだった。
だが、言われたことはわかった。
地元の事件を見逃すとはなにごとか。
ただちに取り押さえよ。暴徒の射殺は可。判断は適宜おこなえ。
適宜って。そんな判断が自分にできるのか。
駐在は自分の頭に手を当てた。すると別のことに気づいた。
帽子を忘れてきた、正式の出動なのに。
そのとき、一茶が腕を伸ばして人差し指をこちらに向けた。
親指を立てているのは、ピストルに擬したからか。
「やれ撃つな、だったかな」
またも、からかうような一茶の笑い。
撃つなと言われても、こちらはまだピストルを抜いてもいない。ホルスターのボタンさえ外してない。だが挑発されているのはわかる。ふるえながら腰に手を伸ばす駐在員。
小林一茶が祈るように両の手のひらをすりあわせる。
どういう意味の動作なのか。
蝿が手をする足をする──。
そんな句があったのを駐在は思いだす。一茶の句だ、きいたことがある。
蝿が手足をすりあわせて命乞いをしている、かわいそうだ、許してやれ──そんな意味の句だったとおもう。
ということは、一茶は自分の句を持ちだして命乞いをしてるのか。だが、笑っているようにも見える。目尻まで下がっている。もしかすると、ほんとうは優しいやつなのではないか。いままで偉そうにしてたのに、こんどは命乞いか、いや、やはり悪いやつに見えるが…。
混乱する駐在員を、一茶の合図を受けたロードローラーが襲う。
たちまち巨大なローラーに押し倒され、自転車ごとすりつぶされる駐在員。
そしてまたも信州でパルチザン発生の報。
駆けつける近隣の駐在員たち。
「三度目は喜劇かね、惨劇かね」
襲いかかるブルドーザー。
さらに凶悪化する小林一茶の笑い。
「すみやかに鎮圧せよ」
県警からの電話でどやしつけられ、自転車で現場にむかう村の駐在。
鎮圧だって? パルチザンの鎮圧なんて、県警での訓練でもやったことがない。手順書などで見たおぼえもない。どうしたらいいんだろう。
考えがまとまらないまま、巡査は自転車を農家の庭に走り入れる。
縁側に腰かけて、小林一茶がこちらを見ている。
「一度目は悲劇として、二度目は喜劇としてだったかな」
ニヤリと笑う一茶。
「短絡だよ、俺が茶なんか立てると思うか?」
はぐらかされて対応に迷う駐在。
とても自分の手に負える人物ではない。一茶の笑いに射すくめられて駐在員はそう思う。インテリは苦手だ。しかもパルチザンの組織者だという。駐在所でふだん付き合ってきた村人とちがい、考えてることが見えない。けれども、ずる賢くて凶悪、そんな感じはする。どうしたらいいのか。それにパルチザンの蜂起が事実なら──どうも事実らしい──村の駐在ごときが扱える事件ではない。機動隊か自衛隊の出番ではないか。
駐在所に残してきた家族のことが脳裏をよぎる。
妻と二人の娘、それに駐在の四人で朝の食卓を囲んでいたところだった。
おかずは納豆、ノビルの味噌和え、タクワン漬け、フキノトウの吸い物、それに今朝は下の娘の誕生日ということで、山間の駐在宅としては多少おごった上等なアジの干物。
「おいしいね」と娘はよろこんでくれた。
下の娘は中一、上の娘は中三。
親の欲目で見てもせいぜい十人並の器量の娘たちだが、性格は悪くない。いや、特別な良い子たちだ。警察官の娘として恥ずかしくないしつけもしてある。勉強だって、そこそこの成績はもらってる。年ごろだから、クラスメートや先輩の男の子たちのことで彼女らが気もそぞろなのはわかっている。でも、それはそれ。けして軽はずみな行動に走るような子らではない。
県警から電話が入ったのは、駐在が「では、父さんも」と尾頭付きのつもりのアジに箸を伸ばしたところだった。
電話をかけてきたのは県警の幹部だった。それを知ったとたん、相手の名前は吹き飛んでしまった。幹部と直接話すなど、そんなことは一生ありえない──はずだった。
だが、言われたことはわかった。
地元の事件を見逃すとはなにごとか。
ただちに取り押さえよ。暴徒の射殺は可。判断は適宜おこなえ。
適宜って。そんな判断が自分にできるのか。
駐在は自分の頭に手を当てた。すると別のことに気づいた。
帽子を忘れてきた、正式の出動なのに。
そのとき、一茶が腕を伸ばして人差し指をこちらに向けた。
親指を立てているのは、ピストルに擬したからか。
「やれ撃つな、だったかな」
またも、からかうような一茶の笑い。
撃つなと言われても、こちらはまだピストルを抜いてもいない。ホルスターのボタンさえ外してない。だが挑発されているのはわかる。ふるえながら腰に手を伸ばす駐在員。
小林一茶が祈るように両の手のひらをすりあわせる。
どういう意味の動作なのか。
蝿が手をする足をする──。
そんな句があったのを駐在は思いだす。一茶の句だ、きいたことがある。
蝿が手足をすりあわせて命乞いをしている、かわいそうだ、許してやれ──そんな意味の句だったとおもう。
ということは、一茶は自分の句を持ちだして命乞いをしてるのか。だが、笑っているようにも見える。目尻まで下がっている。もしかすると、ほんとうは優しいやつなのではないか。いままで偉そうにしてたのに、こんどは命乞いか、いや、やはり悪いやつに見えるが…。
混乱する駐在員を、一茶の合図を受けたロードローラーが襲う。
たちまち巨大なローラーに押し倒され、自転車ごとすりつぶされる駐在員。
そしてまたも信州でパルチザン発生の報。
駆けつける近隣の駐在員たち。
「三度目は喜劇かね、惨劇かね」
襲いかかるブルドーザー。
さらに凶悪化する小林一茶の笑い。